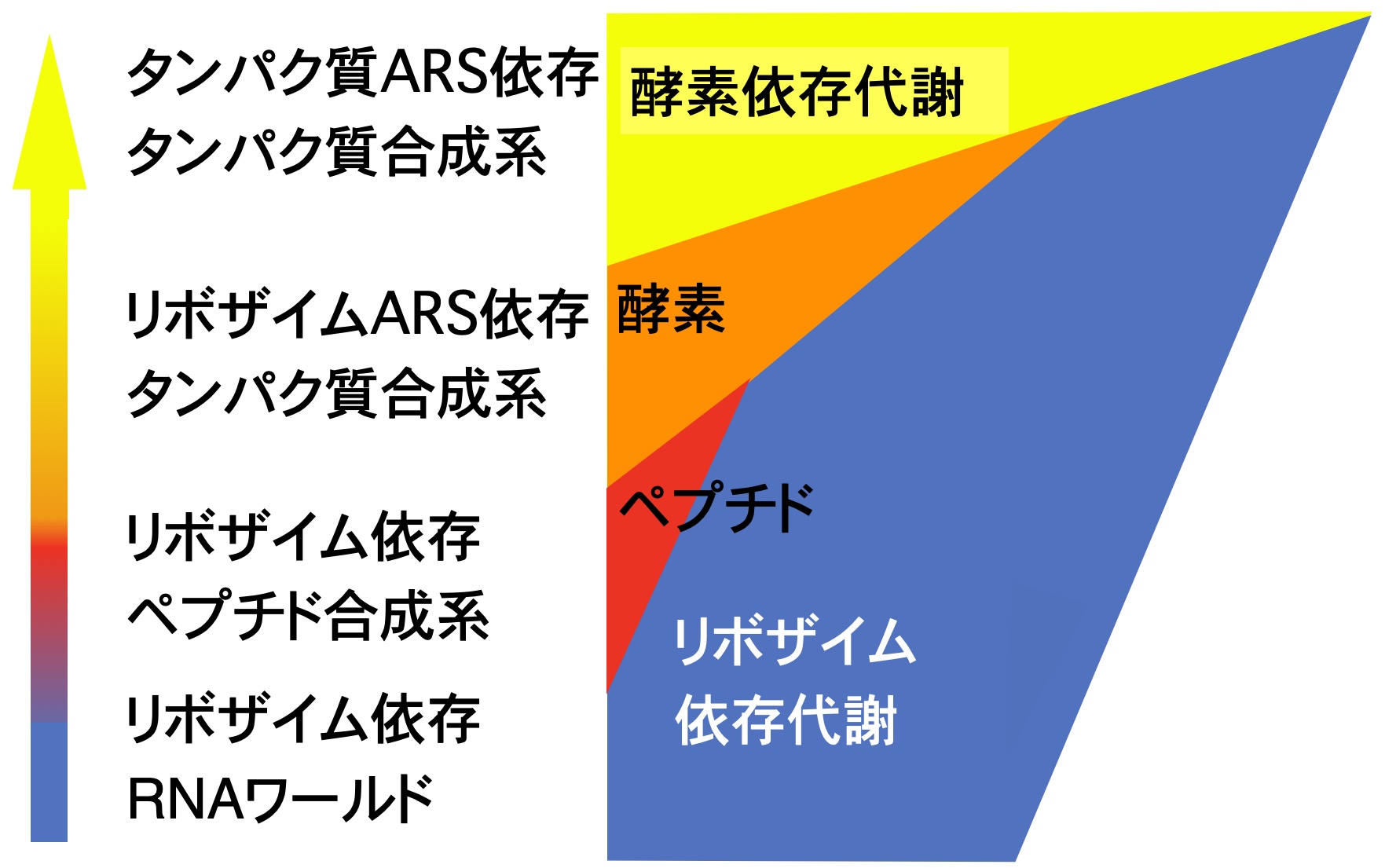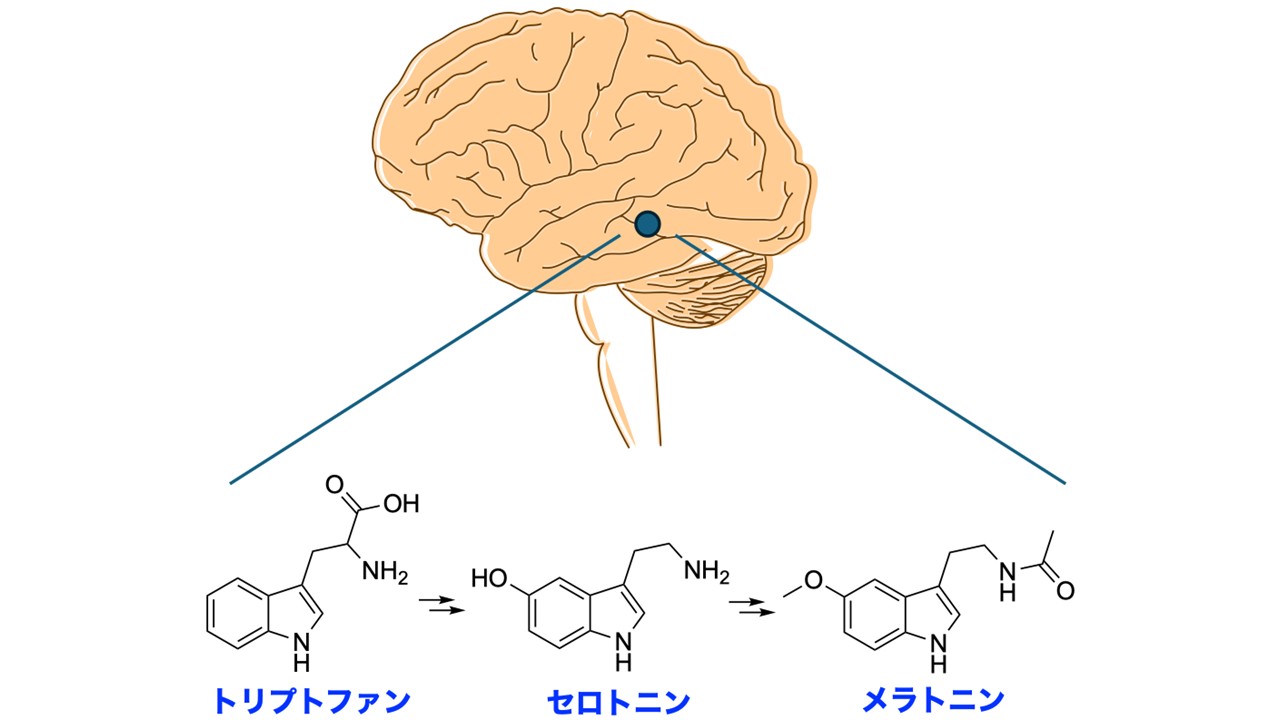実験は何のためにおこなうか
実験研究では、何かの可能性があるとき、そうであるか否かを確認するために実験する。そうであるかもしれないがそうでないかもしれない、ということである。それを確かめるために実験する。
研究では試行錯誤を行う
研究では、基本的には試行錯誤を行う。試行錯誤とは、ともかくも試して、間違っていたらやり直すという方法である。ただし、実験研究の場合には、実験の手間や費用、時間がかかるので、試行錯誤のノウハウがある。
新しい実験装置と技術
研究を進めるためには、まず実験装置と技術がないと始まらない。その研究者の研究室や研究機関が持っている実験装置と技術が、研究を進める上での前提となる。
しかし、もし新しい実験装置や新しい技術があると、新しい知識を得る可能性が高くなる。新しい実験装置や技術が、研究発展の鍵になる場合は多い。研究者は、どこかで開発された実験装置や技術を導入できないかを常に考える。開発能力(開発担当者、技術知識、資金、場所、時間)があれば、新しい実験装置や技術を開発することも大変重要な研究課題となる。新しい実験装置や技術が重要である。
頭の中での試行錯誤
実験する前に、頭の中で徹底した試行錯誤を行う。研究者の経験と知識はここで役にたつ。それまでに、自己および他の研究室で得られた実験結果と、そこから得られた知識が研究者の頭の中には詰まっている。無数の研究者によって長い年月をかけて得られた膨大な実験結果と、そこから得られた知識の総体を知識の体系という(名誉教授コラム「自然科学の体系」参照)。知識の体系に基づいて、どの様な可能性があるのかを頭の中で「あーでもないこうでもない」と試行錯誤をして考える。
この段階では、可能性をすべて考え尽くすことが重要である。この段階では、可能性の低いことも除外せずに、すべての可能性を考え尽くす。その全ての可能性の中で、可能性の高そうなこと、技術、費用、時間的にやりやすいことから順に実験で確認していく。
やってみなければ分からない
そして、ともかくも実験を実施することが重要である。確かめなければ何も分からない。実験してみなければ、何が分からないのかすら分からないことも多い。徹底的にそれまでの知識を動員して、頭の中でとことん検討して、最後は実験してみる。
安価で時間のかからない簡単な実験であれば、考えるより先に試した方が良い場合もある。その場合にはそうすべきである。最も貴重なのは時間で、早く結果がでて早く論文発表できれば、その知識は早く世界の研究者の知るところとなる。その知識が世界の研究推進の参考になる。
失敗しても良い、やり直せば良いのだ
実験は、何かを確かめるために行うので、それを確かめることのできる方法と精度が必要である。それは技術的に難しい場合も多く、失敗する場合も多い。しかし失敗したらやり直せば良い。
失敗した実験は無駄ではない。実験で失敗することによって、本格的に何かを実施して失敗した場合の無駄を大いに省いていることになる。小さな無駄を積み重ねることにより、大きな無駄を避け、より大きな成功に繋がると考えて良い。小さな無駄をケチることは、大きな成功の機会を逸失していることになる。
実験者の原動力
また実験者のやる気は、実験がうまく進むかどうかの非常に重要な因子になる。この実験で何かが明らかになりそうだと思うと、実験者は興奮する。もし何かが明らかになればその瞬間に、その実験者は世界でただ一人その事を知る人になる。その後で誰かに結果を知らせたとしても、その実験者はそれを最初に知った人になる。この思いは大変強く、実験者が実験を行う強い原動力となる。
戦略的に考える
研究者がその実験装置や技術を持ち合わせていない場合、実験技術が難しい場合、実験装置や試薬が高額である場合、実験に長期間かかる場合等には、戦略的に考える必要がでてくる。その技術を良く知っている研究者と共同で実験できないか。実験装置を借りる可能性はないか。研究資金を入手する可能性はないか。自分の時間をどの程度その研究につぎ込むか。実験によって分かることの意義と重要性等を考え合わせて、方法と計画を戦略的に考える。
実験費用と実験にかかる時間は重要な項目である。低額で短期間で実験が行えれば、もちろんその方が良いが、知識の体系を発展させるために必要であれば、費用と時間をかけて多人数で研究を実施する価値がある。こうした研究は大型研究と呼ばれる。大型研究を進めるためには、戦略的に計画を立てる。
実験結果は実験結果
ただし、これらの因子が、実験結果の解釈に影響を与えてはいけない。高額の費用、手間と時間をかけて、実験者が非常な熱意を持って実験すると、期待した様な結果になって欲しいという気持ちが強くなってくる。しかし、実験結果は実験結果、それを冷静な目で見て、その結果が何を意味するのかを判断する必要がある。これが最初に書いた、そうであるか否かを確認する、ということの意味である。そうであるかもしれない、そうでないかもしれない。