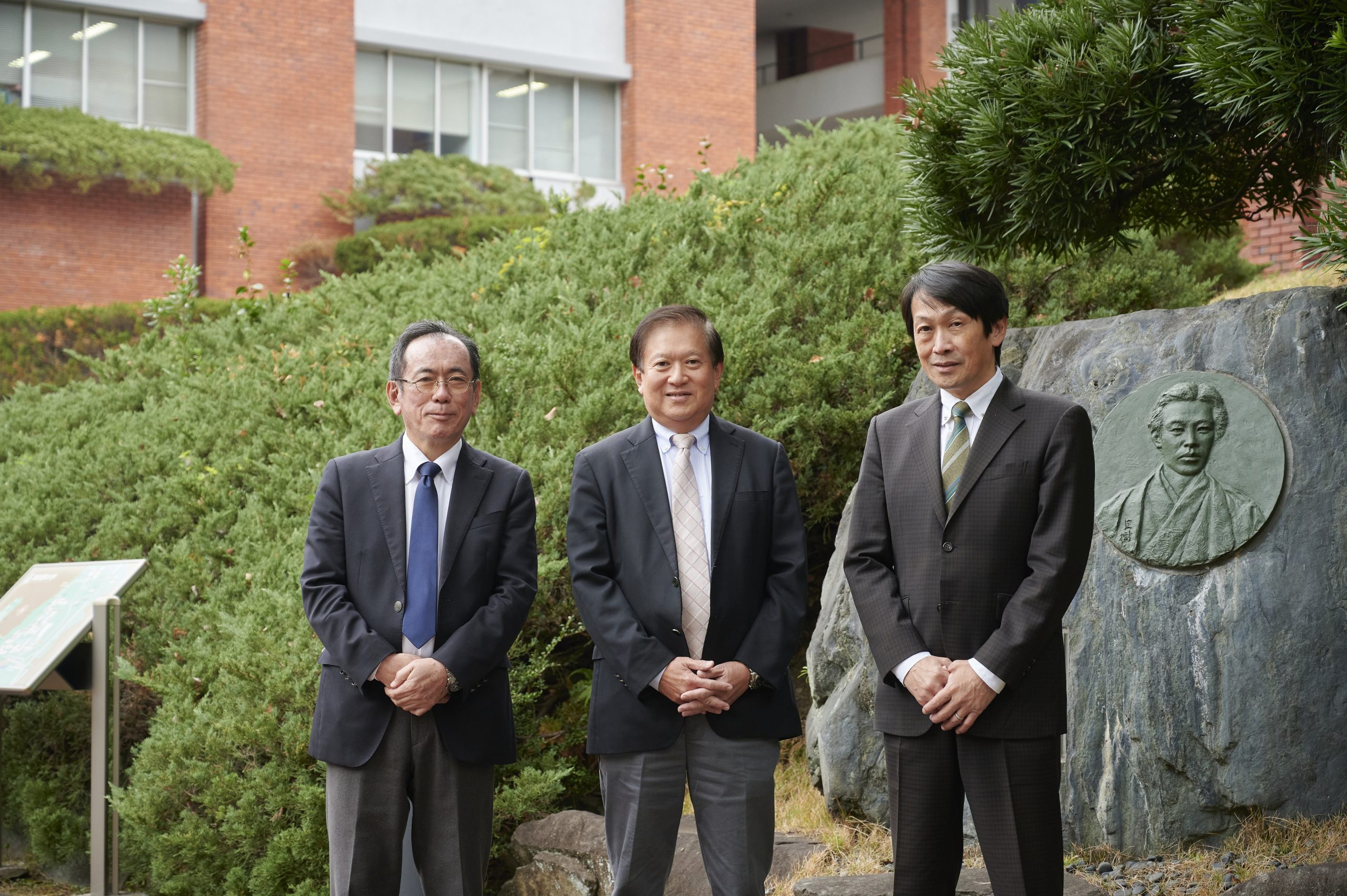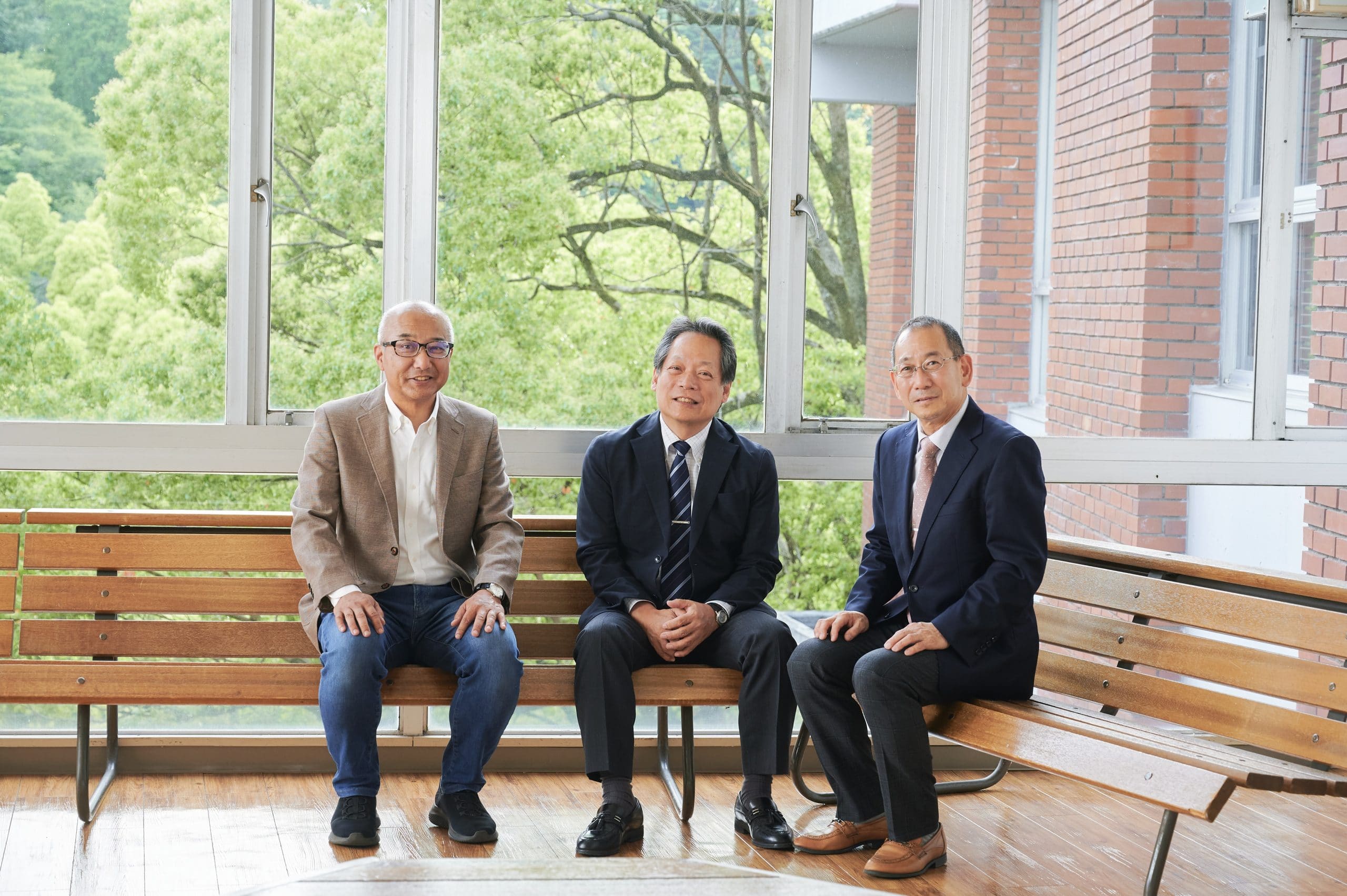東京薬科大学が有する広範なナレッジ、アイデア、技術を提供することで、創薬関連企業における学術的・技術的ニーズの充足に貢献し、同時に学内外における人材育成に貢献することを目的として、2023年4月、「東京薬科大学創薬エコシステム」が発足しました。代表世話人の石原比呂之教授、世話人の栁田顕郎教授、そして学外の視点でアドバイザーを務める高橋雅行客員教授が、本コンソーシアムの狙いと展望を語り合いました。
代表世話人 石原 比呂之(薬学部 教授)
世話人 栁田 顕郎 (薬学部 教授)
アドバイザー 高橋 雅行 (薬学部 客員教授)
企業と東薬をつなぐプラットフォームを創る
石原 まず「東京薬科大学創薬エコシステム(以下、創薬エコシステム)」設立の経緯からお話しします。私は2021年に本学に着任するまで、長く製薬会社で研究してきました。主に製剤や原薬物性を研究し、物性探索から薬事申請にまで携わりました。本学では、ナノサイズの粒子を利用したDDSに関する研究を進めています。一方で、本学で培われてきた高い研究力をもっと創薬に生かすために何かできないか、という思いがあります。これまで企業で築いてきたネットワークや、創薬に関わってきた経験を活かし、創薬研究における具体的なニーズと本学の持つナレッジや技術を繋ぎ合わせるための「土俵」を作りたいと考え、このコンソーシアムの設立を提案しました。まずは薬剤やDDS、分析など、製剤化技術や分析技術といった汎用性のある分野から議論を始められたらと思い、東薬でそれらに関係する研究に携わっている先生方に集まってもらいました。
栁田 私は世話人の一人として発足メンバーに加わりました。私は約10年間、酒造会社に勤めた後、大学で研究に従事してきました。一貫して新しい分析法の開発をテーマに研究しています。まさに今、最前線で研究されている製薬会社の方々と一緒に研究することになり、改めて新鮮な気持ちで臨んでいます。
高橋 私も30年以上を製薬会社で過ごし、製剤からDDS、物性、動態など幅広く研究してきました。2023年4月には起業し、現在はベンチャー企業としても創薬に関わっています。創薬エコシステムのアドバイザーとして参画した理由の一つは、企業の若い研究者たちに、社外で新しい研究にチャレンジするチャンスをつくってあげたいという思いがあったからです。製薬会社では、以前に比べて製薬企業間の交流や技術系企業との関わりが減っていることに課題を感じていました。創薬エコシステムに、企業の若い方々が参加し、新しいアイデアや豊富なナレッジをお持ちのアカデミアの研究者と意見を交わすことで、発展的なコミュニケーションが生まれるのではないかと期待しています。
製薬企業8社、技術系企業4社が参画し、コンソーシアムが始動
石原 2022年夏に世話人会を中心に準備を開始しました。2023年4に本学主催コンソーシアムとして発足し、同年12月までに製薬企業8社、技術系企業4社の計12社に参画していただいています。会員企業を中心に様々なニーズを吸い上げ、それに応えるインフラに育てていけたらと考えています。
栁田 製剤系企業や分析系企業は、会社の枠を超えて連携しやすいという印象を持っています。創薬エコシステムで有意義な連携が生まれそうで、楽しみです。
石原 創薬に直結する化合物の研究は企業間で競合しますが、製剤技術や分析技術に関しては共通のプラットフォームで知見や情報を共有しやすいのではないでしょうか。2年目以降、さらに多くの企業に参画していただけるよう力を入れていくつもりです。
高橋 企業の立場で期待しているのは、アカデミアの研究者たちに、合成の難しいペプチドや誘導体、試薬など、共通の研究ツールになり得るものをつくっていただくことです。また、例えば類似したペプチド化合物で、消化管吸収される化合物とわずかな構造の違いで吸収されなくなるといった課題を提供していただくことも一つです。それを研究材料に、皆で知恵を出し合えば、評価法やメカニズム解明等のユニークな研究に発展させられると考えています。
栁田 企業の方々が興味を持って研究したくなるような「ネタ」を提供することが、第一歩だと考えています。そのため先日開催した第1回シンポジウムでは、学会では取り上げられていないテーマを意識して用意しました。おかげで当日の発表では多くの質問が飛び、また事後アンケートにも多くの記述をいただくなど、大きな反響がありました。
石原 第2回は創薬ツール、第3回は、DDSや吸収をテーマにシンポジウムを開催していくことを考えています。東薬の先生方の参加者も増やしていきたいですね。若い研究者の方々にとっては、企業とのネットワークをつくるチャンスです。ぜひそうした目的意識を持って参加してもらえたらと思っています。
企業のニーズ、大学のシーズを持ち寄り、研究を広げる
栁田 今後、創薬エコシステムから製薬業界に貢献する製品などのアウトプットを出していけたら、大きなアピールになりますね。
高橋 企業で新しい試薬や評価系が開発されても、担当者の目的にそぐわなければ、「使えない」とレッテルを貼られてしまいます。しかし十数社が集まってそれぞれ異なる観点から検討すれば、他の目的においては極めて重要な意味を持っていたり、別の用途では非常に便利なツールになることもあります。企業と大学がアイデアやツールを持ち寄り、それをみんなで検討し、データを共有すれば、効率的により多くの情報を得られます。さらに技術系企業に加わっていただければ、具体的なツールを開発することも可能になります。今後創薬エコシステム内でのコミュニケーションが活発化し、研究が広がっていくことが楽しみです。
石原 同感です。高橋さんがおっしゃるように、企業の方々もさまざまなニーズをお持ちだと思います。創薬エコシステムに持ってきていただき、一緒にアウトプットにつなげていきたいですね。
高橋 一方で、東薬からも「これは」と思うシーズを出していただけると、より発展していくと考えています。これまで企業の目に触れることなく大学に眠っているすばらしい技術や知見が数多くあるはずです。お互いのニーズとシーズを出し合えたら、おもしろい研究が生まれると思います。
栁田 研究力の高さが、東薬の持ち味です。本学の研究者が多く参画することが、本学の研究の底上げにも役立つと考えています。
石原 今後、さらに企業、そして学内の研究者の参画を増やし、活気あるプラットフォームを構築していきたいですね。