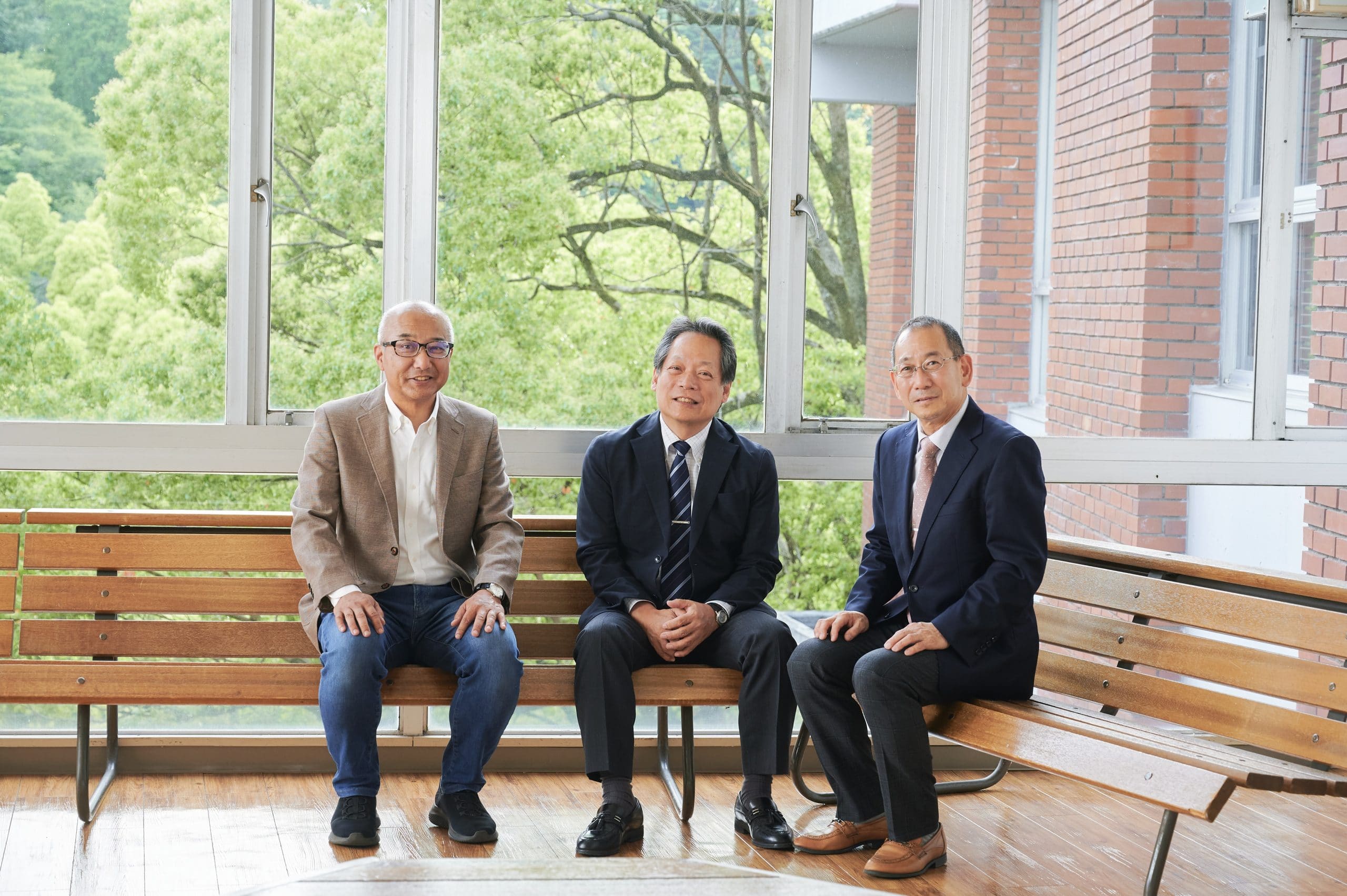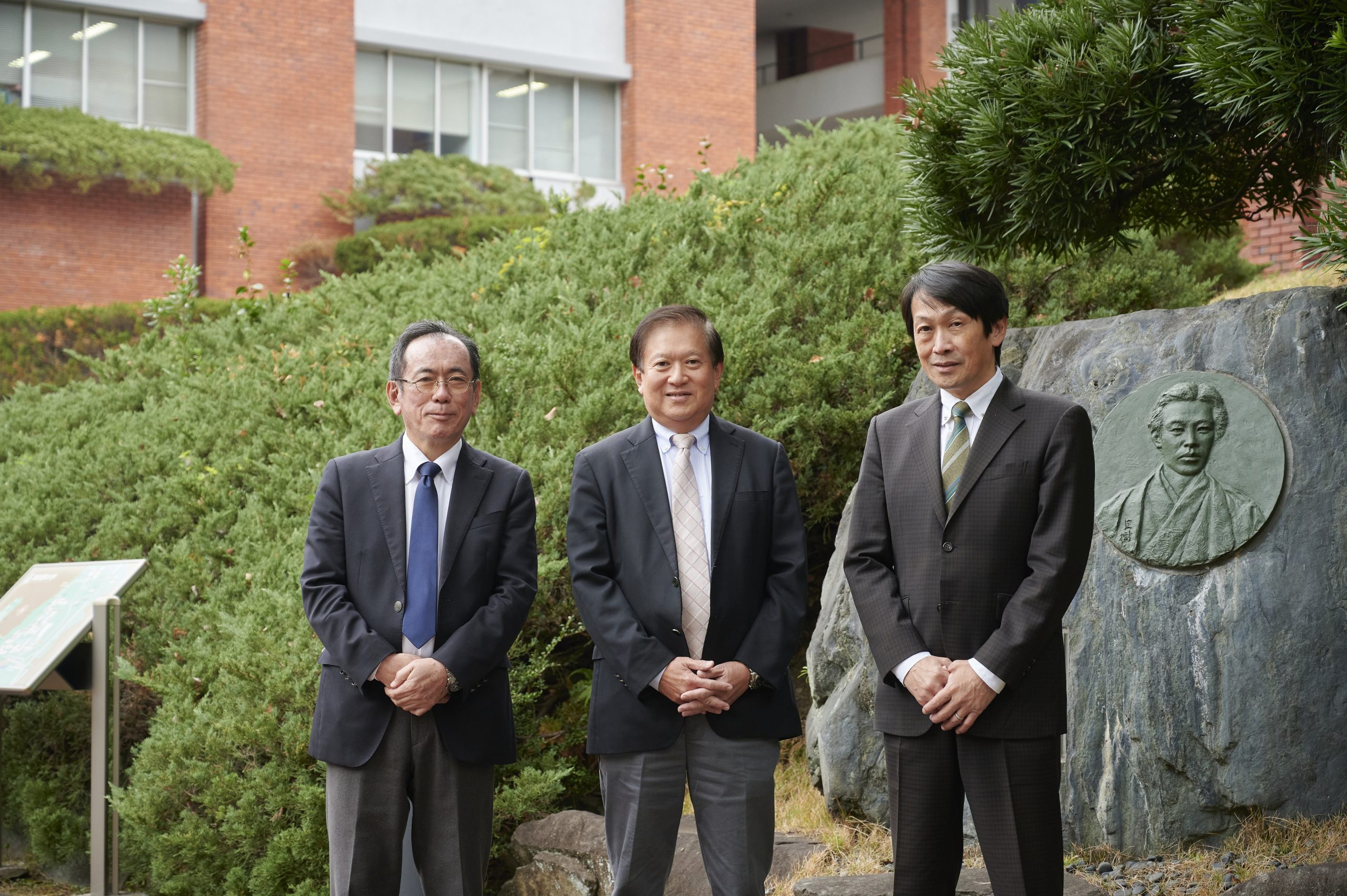東京薬科大学は、2021年、研究推進機構を発足し、薬学部・生命科学部による共同研究の強化と産学連携、若手研究者育成を推進してきました。2024年4月、さらなる研究の発展を目指して組織改編。未来創薬研究所、臨床薬学研究センター、プラネタリーヘルス研究コアを拠点に、「研究の東薬」として、飛躍を遂げようとしています。
研究推進機構 機構長 林 良雄(生命科学部 教授 薬学部 特命教授)
イノベーション推進センター センター長 渡邉 一哉(生命科学部 学部長 教授)
副学長 山田 純司(薬学部 名誉教授)
両学部の共同研究と産学連携、若手研究者育成を目指す新機構を発足
――2021年に研究推進機構を設立した経緯とこれまでの活動についてお聞かせください。
林 本学は、個々の研究者の研究力の高さには自信を持っていました。これまでにも研究者の研究プロジェクトがAMED※1や創薬等先端技術支援基盤プラットフォームの事業に採択されるなど、多くの実績を挙げています。一方で、学部を超えた共同研究を推進する体制については、十分とはいえなかったのではないかと思います。そこで本学の特色である研究力を強化するとともに、薬学部・生命科学部の共創的活動と若手研究者育成を目指すため、2021年、研究推進機構を発足しました。
渡邉 研究推進機構に先立って活動してきたのが、イノベーション推進センターです。目的は、本学の研究資源を外部へと橋渡しすること。産学官連携の推進と、それに伴って不可欠となる知的財産の管理・技術移転体制を構築する役割を担っています。現在は、知的財産の創成に加え、展示会への出展、研究広報誌『CERT』の発行など、さまざまな形で研究成果を外部に発信しています。そのほかにも、日本科学未来館の入居プロジェクトや、高大連携活動など、幅広い取り組みを展開しています。
山田 薬学部・生命科学部の共同研究の充実は、長く本学の課題でした。研究推進機構の設立は、まさに悲願達成といえますね。
林 もう一つの共同研究センターは、若手研究者育成を目的に据えています。設立の背景には、大学院博士後期課程を対象とした未来医療創造人育成プロジェクト「BUTTOBE」が、JST※2の「SPRING※3」に採択されたことがあります。「BUTTOBE」を通じて、力のある若手研究者を育成する素地をつくれたことが、本センター設立の後押しになりました。これまでに薬学部と生命科学部の若手研究者の共同提案で研究する「萌芽的研究ユニット」を立ち上げ、研究支援に取り組んでいます。研究推進機構の下、3年間、機器整備などのハード面、人材育成といったソフト面、さらに産学連携を充実させてきました。特許出願件数や外部資金の獲得金額、受託研究数など、その成果は数字にも如実に表れています。
臨床薬学、プラネタリーヘルス研究へ、研究領域を広げる新体制
――2024年4月、研究推進機構の下に、イノベーション推進部門、及び研究施設・機器管理部門に加えて、新たに総合先端研究部門を設立。同部門に未来創薬研究所、臨床薬学研究センター、プラネタリーヘルス研究コアを設けました。
山田 研究推進機構設立の背景にはもう一つ、薬学部に6年制が導入されて以降、大学院進学者が減少し、本学の基礎研究に対する危機感が募っていたこともありました。研究推進機構が動き出して3年間で、この課題は克服しつつある中、次の課題として目を向けたのが、現在国を挙げて推進されている臨床薬学です。これについてもしっかり育てていくべく、創薬研究所、そして臨床薬学研究センターを設立しました。現在、医療機関とも積極的に連携し、がんや感染症、災害医療などをテーマに研究実績を重ねています。さらにもう一つ、かねてから重要だと考えていたのが、「生活者」を対象にした研究です。患者の命を救う医学・創薬に加え、生活者の健康を守ることまで視野を広げた研究が求められています。それが、「プラネタリーヘルス研究コア」創設につながりました。
学術・研究のハブとして、地域連携・大学院教育にも尽力する
――今後の展望をお話しください。
林 これまで東京薬科大学は、教育に力点を置いてきましたが、2024年、いよいよ学問の府として、研究を中心に置いた体制が整ったと自負しています。とりわけ心強いのは、大学からの力強い肯定と後押しを得られたことです。研究機器の管理・購入といった資金運用の権限が、本機構に一任されていることもその一つです。もちろん大学の経営資源が投下されている分だけ、責任も重大だと認識しています。その期待に応える成果を挙げていかなければと、気を引き締めています。
渡邉 イノベーション推進センターとしては、特許の出願・取得だけでなく、それを企業との共同研究につなげ、社会実装によって収益を上げるところまでを目指しています。特許出願から企業連携による社会実装まで達成し、収益によって次の特許出願の資金を確保する。その好循環をつくりたいと考えています。そのためには基礎研究と同時に、その成果を産業・技術につなげていく研究にも力を注ぐ必要があります。本センターが中心となって、研究者の意識改革とともに、例えば、「この研究にこの実験を加えたら、特許出願の道が開ける」といった研究手法に関するアドバイスや支援も行っていくつもりです。
林 研究を通じて大学のある多摩地域に貢献することにも力を注ぎたいですね。この地域には、プラネタリーヘルスに関わる企業も多く、産学連携のチャンスは豊富にあります。研究推進機構が多摩地域の学術・研究のハブとなり、地域連携を推し進めていきたいと考えています。
山田 研究成果の「出口」としての地域連携に加えて、本学を「入口」とした地域連携も可能ではないでしょうか。これまで地域の医療機関などから課題や研究シーズが持ち込まれても、適切な受け皿を用意できないことがありました。本機構なら、そうした受け皿の機能も果たせるはずです。2024年、本学とBCRET※4の連携によるバイオ人材育成の取り組みが始動しましたが、これはまさに本学が「入口」となった好例です。さらには学外だけでなく、学内の研究交流を促進することも期待しています。薬学部と生命科学部の大学院生が交流し、お互いの研究について理解を深める機会をつくることで、共同研究や連携のチャンスを増やしていけたらと考えています。
林 確かに本機構が大学院教育に果たす役割は大きいと思っています。今後、大学院生の研究の高度化にも貢献していくつもりです。これからの本機構の研究・教育にご期待ください。
※1 AMED:国立研究開発法人日本医療研究開発機構
※2 JST:国立研究開発法人科学技術振興機構
※3 SPRING:次世代研究者挑戦的研究プログラム
※4 BCRET:一般社団法人バイオロジクス研究・トレーニングセンター