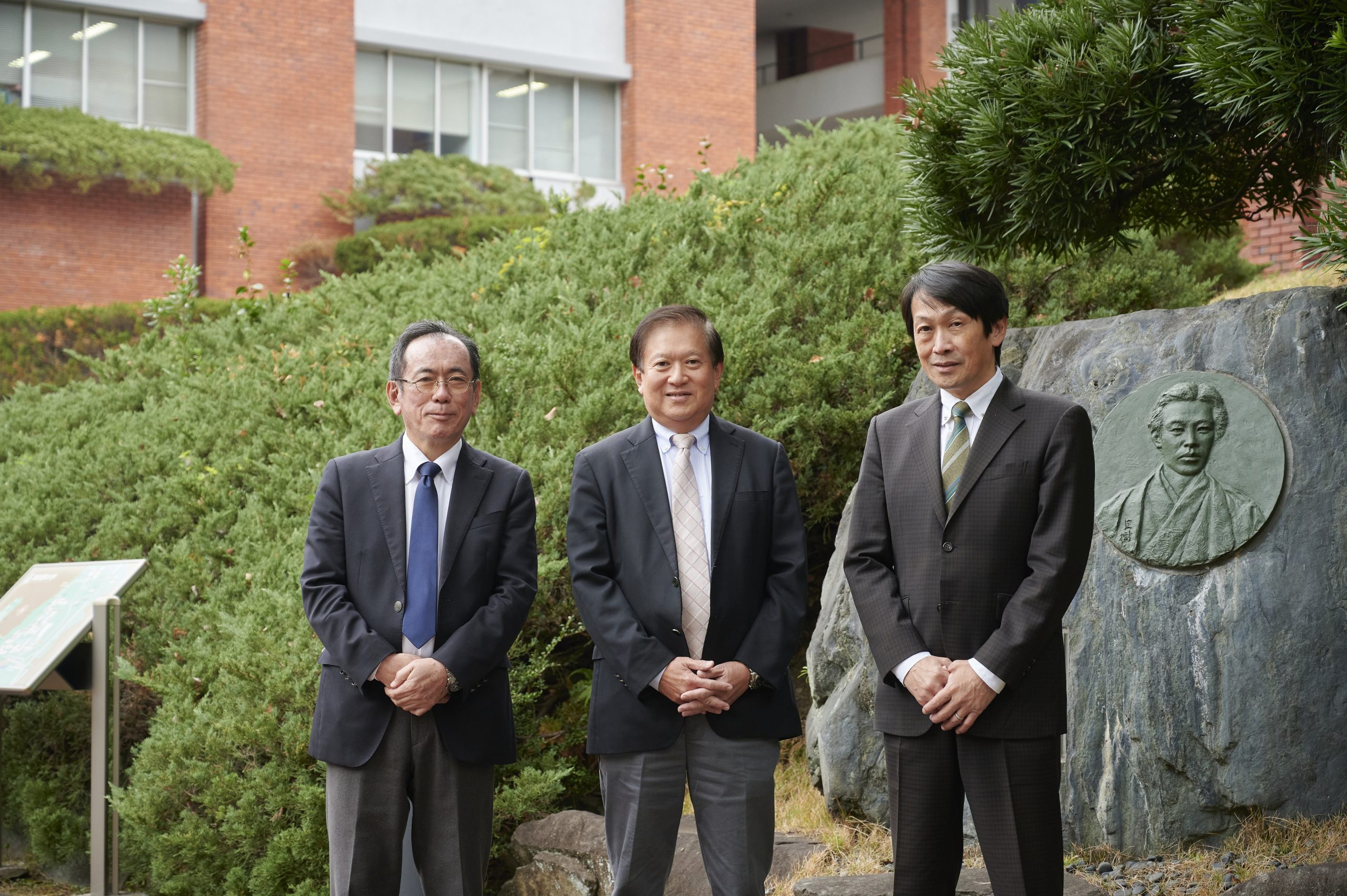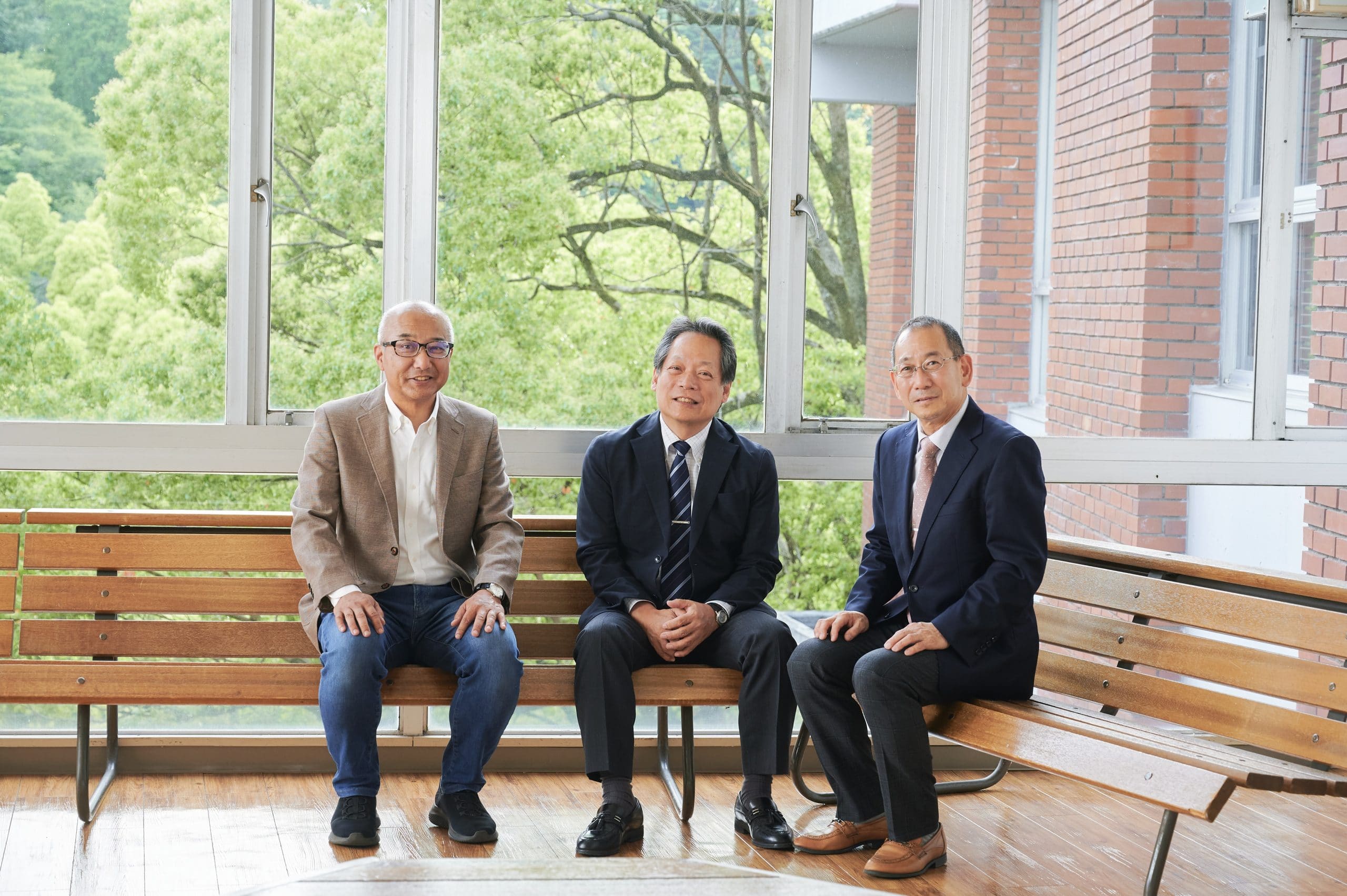プラネタリーヘルス(PLH)は,2015年にランセット誌に掲載された論文をきっかけに拡散された言葉で,人間と社会の健康と地球と生態系の状態とが相互依存することを意味する.これは言ってみれば当たり前のことなのだが,その当たり前がいつの間にか影が薄くなった結果として,国連の言うTriple Planetary Crisis (気候変動,生物多様性の減少,環境汚染)が起こり,人類がその脅威に晒されているというのが現状と言える.PLHはこの当たり前を再認識し,社会のあり方にも大きなメスを入れて3つの危機を解消することを目指す「研究と社会活動の総体」を指す言葉でもある.3つの危機はいずれも人類の存続に関わりかねない深刻な問題であり,手を打たない限りは悪化し,いずれ後戻りのできないtipping point に到達することが懸念されている.一方で,様々な格差や人口の高齢化,感染症の勃発といった経済や社会の問題への対策が,3つの危機の解決に通じるという,いわゆるコベネフィット的な出口が見つかる可能性もある.
これらの危機がいずれも人間活動に起因することが明確になってきたのは,ある意味で救いと言える.というのは人間活動―大きく言えば文明(civilization)―のあり方を変えれば,これらの危機も軽減・解消されることープラネタリーヘルスが実現されることーを意味するからである.研究者の間には,解決のための知見は十分に存在していて,知見と実践を結ぶ方法の欠如が解決の障害になっているという指摘も多い.となると解決のために必要な条件がいくつか浮かび上がってくる.第一に私たちの生活のあり方が3つの危機を招いたということを,社会を構成する人が理解していること,第二に政治や経済活動のリーダーがこの問題を意識し,解決の意欲をもっていること,第三に解決の方向性を示す科学的知見があり,それを人々に伝える術があること.
大学はこの解決―プラネタリーヘルスの実現―のために何ができるだろうか.第三の条件=科学的知見の蓄積=は大学本来の業務で,その最も得意とするところだろう.新たに必要なことは,自分の研究がこの解決のスキームにどう貢献できるのかを考えること,逆に知見のギャップを見つけてその研究を進めること.時には自分の研究が解決を妨げるものでないか―温暖化を促進したり,生態系を破壊したりという結果に結びつかないか―疑う必要が出てくるかも知れない.一方で第三の条件の後半―知見を人々に伝える術―については,研究者はこれまで十分訓練を積まず,むしろ軽視してきたと言っていいだろう.個々人の努力もだが,この部分に特化した教育・訓練の方法を開発する大学としての努力が必要と言える.そのような個人・大学の努力を通じ,アカデミアの外と対話する研究者が増えることによって第一,第二の条件整備にも貢献できるだろう.この場合,研究者の役割は啓発ではなく対話であり,研究者として科学的知見を提供すると同時に,ノンアカデミアの経験知を受容することが肝要になる.
プラネタリーヘルスの実現には,地球(生態系を含む)を意識し,将来世代を意識し,systems thinking を心がけることが重要とされる.薬学の研究と教育の中で,常にこの3つの意識を維持することが,言ってみれば「リテラシーとしてのプラネタリーヘルス」を身につけることであると言えよう.