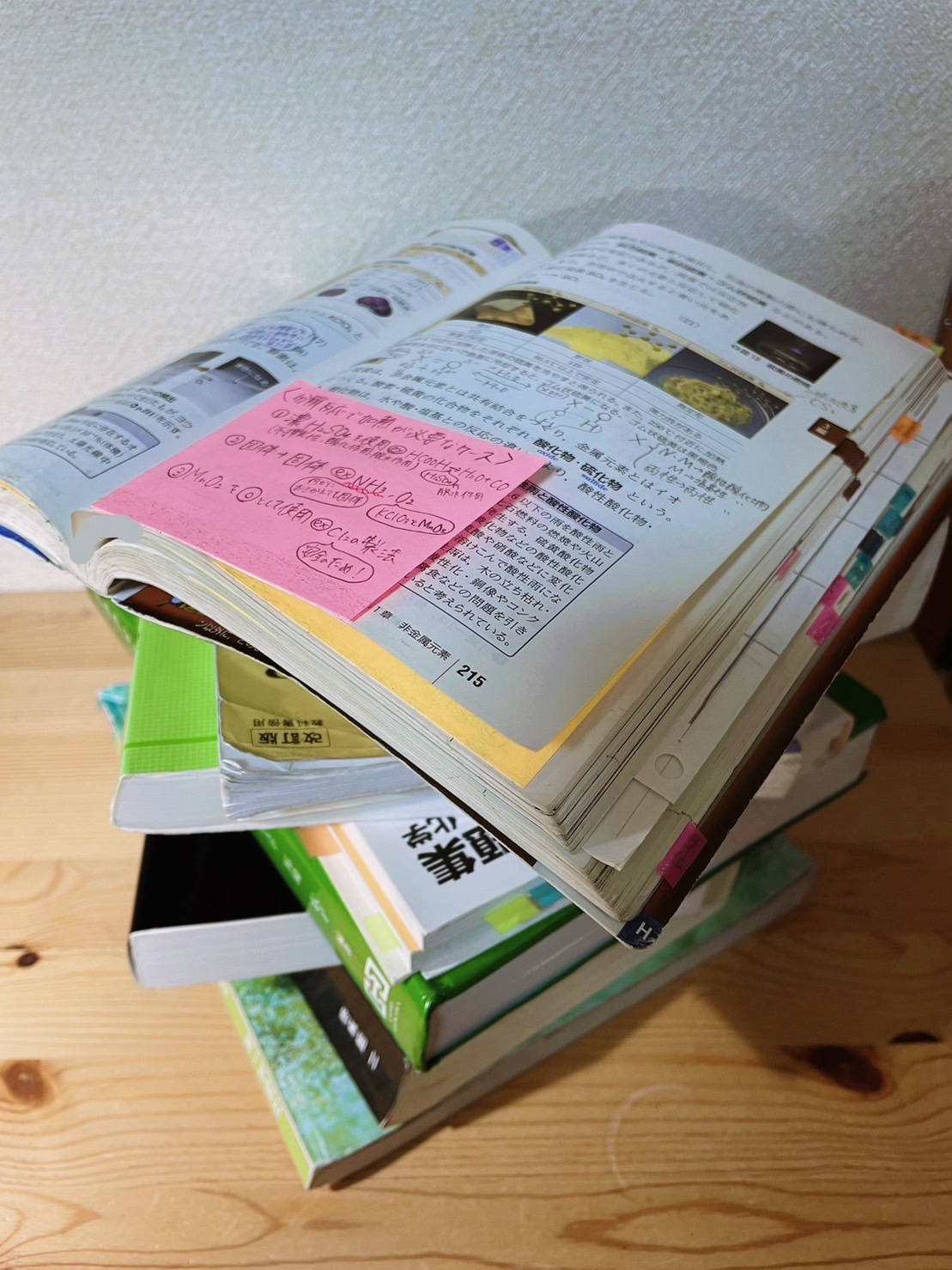私は中学時代、英語を話すことが好きで、将来は国際関係の仕事に就くことに興味がありました。しかし、高校2年生の頃から科学に関心を持ち始めました。
私が通っていた中高一貫校は英語教育に力を入れており、カリキュラムの中で海外研修プログラムや英語でのプレゼンテーションを行う機会がありました。また、個人的にも海外短期留学プログラムに参加し、中学3年生の時にカナダ、高校1年生の時にはフィリピンで、それぞれ2週間ほどの留学を経験しました。現地では積極的にコミュニケーションを図り、語学スクールで実践的な英語を学びました。特に、語学スクールでは日本語の使用が禁止されていたため、日本人同士でも英語で会話しなければならず、自分の考えを相手にわかりやすく伝えることの難しさを実感しました。また、わからないことを素直に伝え、周囲に助けを求める大切さも学ぶことができました。
その後、私が科学、特に食品科学に興味を持つようになったのは、もともと「食べることが好きだった」ことがきっかけです。昔から食べることが好きだった私ですが、家族には体が弱く、持病の関係で好きな食べ物を我慢している人もおり、健康食品やサプリメント、病院食などが話題になることが家庭内でよくありました。私自身も気になる食品やサプリメントについて調べたり試したりすることが増え、「気軽に栄養補給ができ、健康をサポートできる食品がもっと美味しくなってくれればいいなー、じゃあ自分で作っちゃえ!」と思ったことが食品科学への興味を持つきっかけになりました。食品の加工や保存技術を学び、より美味しく、楽しく健康管理ができる食品を作れたらと思っています。
中学時代の私は自信がなく、グループワークで意見を伝えることや人とコミュニケーションを取ることに億劫さを感じていました。しかし、留学プログラムを通じて、自分の意見を聞いてくれる人がいるのなら、しっかり伝えなければならないと気づきました。このような環境がどれほど恵まれているかを実感し、その機会を活用することが重要だと感じました。
この経験から学んだ「わかりやすく伝えることの重要性」は、サイエンスコミュニケーターとしての役割にも深く結びついています。科学の知識は時に専門的で複雑ですが、それをわかりやすく、興味を引く形で伝えることで、多くの人が科学を身近に感じる手助けをすることができます。私の体験から、一方通行ではなく、相手が関心を持ちやすい形で伝えることの重要性を痛感しました。
科学にはそれまであまり興味がありませんでしたが、短期留学などから得た感覚や教訓は、科学の分野や今後の人生においても無駄にはならないと思います。一つの分野にとらわれず、少しでも興味を持ったことには一歩踏み出すと良いと感じています。そうすることで、自信が持て、価値観や見聞が広がり、見える世界が変わっていくと信じています。
(2025SPRING CERT11より)