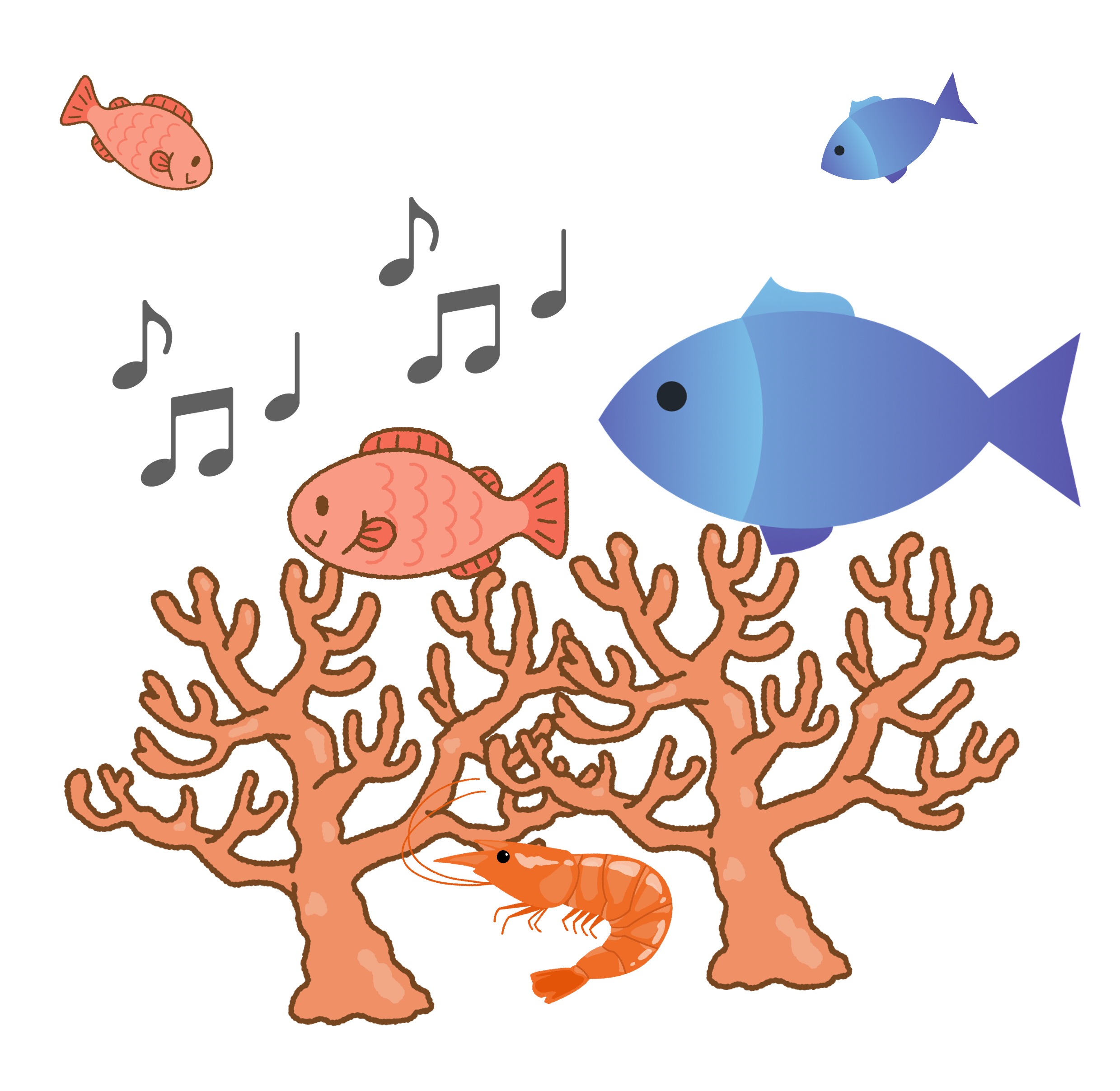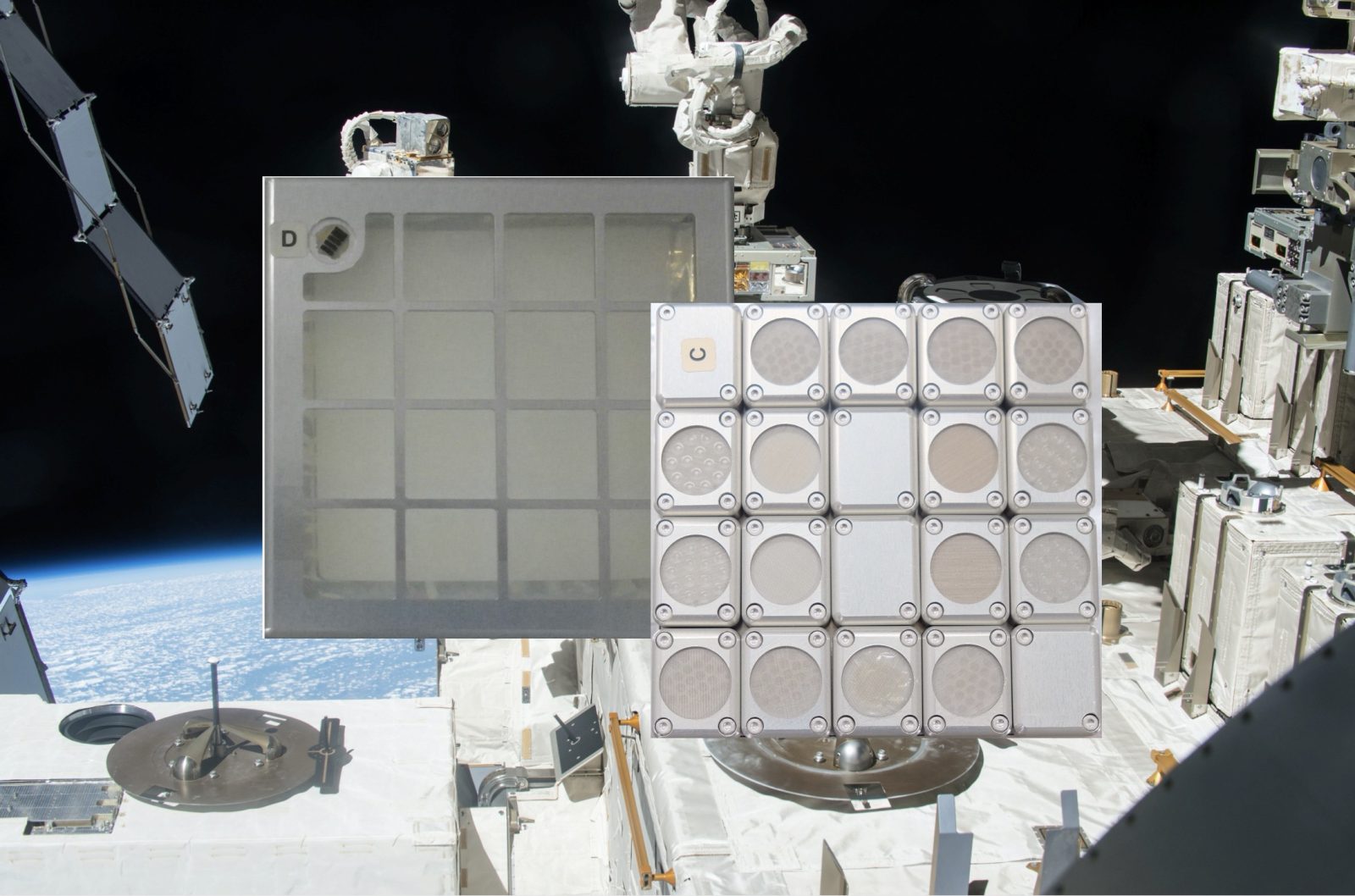私たちの意識の中では、耳に聞こえない音は存在しないものとして扱われがちです。魚やカメの声を耳にしたことのない多くの人にとって、彼らは「寡黙な生き物」と映るのではないでしょうか。少なくとも私はそうでした。
人間の耳に聞こえる音の周波数帯は、およそ20 Hzから20,000 Hzに限られます。しかし、それよりも低い周波数(超低周波)や高い周波数(超音波)を聞き取る能力をもつ生物もいます。人間には聞こえない音を用いてコミュニケーションを行っている例も、近年次々に明らかになってきました。たとえば、ゾウは人間の耳には聞こえない超低周波音でコミュニケーションをとっています(参考1)。
生物音響学(Bioacoustics)とは、生物学と音響学が交わる学際領域であり、音による情報伝達や感覚・行動の生理学、さらには音や振動の物理学・工学までを含みます(参考2)。その研究対象は、陸生の哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類、昆虫から水生の哺乳類や魚類、さらには植物にまで広がっています。
音を発する魚
魚は寡黙 ── 一般にはそのように思われてきました。けれども、魚が音を発することは古くから知られており(参考3, 4)、古代ギリシャの哲学者アリストテレス(前384~前322年)は、著書『動物誌』の中で、ボラやスズキには聴力があり、ホウボウやニベなどは音を出すことを記しています(参考5)。
水中の音は、水上にはあまり伝わりません。音は空気や水といった物質を振動させて進みますが、水中で生物から発せられた音の多くは、水と空気の境界である水面で反射してしまいます。これは、水と空気の性質が大きく異なるためです。したがって、水中の音をとらえるにはハイドロフォン(水中マイク)が必要です。
近年の研究では、人間の耳には聞こえない音も含め、魚が多様な音を発していること、そしてそれらが情報伝達の手段として利用されていることが明らかになってきています。
生物の音に満ちている「沈黙の世界」
かつて海中は、光も届かず、生物の気配も乏しい「沈黙の世界」だと考えられていました。ところが20世紀半ば、軍事技術として開発されたソナー(音波探知機)の受信部であるハイドロフォンの登場によって、そのイメージは大きく変わりました(参考1,3,4)。
音は水中では空気中よりも約4.5倍速く伝わります。特に低周波(長波長)の音は減衰しにくく、数kmから、場合によっては数千km先まで届くこともあります(参考3)。この性質を利用して、海中での音波探知は潜水艦の発見に役立てられました。
ところが、軍事目的で記録された音の中には、潜水艦とは異なる自然由来の音が多数含まれていました。それらはクジラや魚、甲殻類などが発する音であることが、次第に明らかになりました。海は静寂ではなく、実は生物の音に満ちた世界だったのです。1991年の東西冷戦終結に伴って軍事機密が解除されると、海中で記録された音の情報やハイドロフォンが民間の生物学者にも利用できるようになりました。
魚の発する音には、発音筋とよばれる筋肉で浮き袋を震わせて出す振動音と、骨・歯・ヒレをこすり合わせて生じる摩擦音があります(参考3)。また、テッポウエビはハサミを勢いよく閉じることで、水中に190〜210 dBという強力なパルス音を発します。
こうした音は単なる副産物ではなく、生物どうしの重要なコミュニケーション手段と考えられています。求愛や警戒、縄張りの主張など、状況に応じて異なる音が使い分けられている可能性があります。特に夜行性の魚や視界のきかない深海の魚にとっては、音は光に代わる重要な情報伝達手段なのでしょう。
サンゴ礁の音の風景
サンゴ礁は、熱帯・亜熱帯の浅く温かい海に発達する生態系で、石灰質の骨格をもつ造礁サンゴが集まって形成されます。造礁サンゴは体内に褐虫藻とよばれる藻類を共生させており、光合成で得たエネルギーを利用して石灰質の骨格を作ります。こうして成長したサンゴは、世代交代を繰り返しながら骨格を積み重ね、長い年月をかけてサンゴ礁全体を構築していきます。
サンゴ礁は「海の熱帯林」ともよばれ、魚類、軟体動物、甲殻類、海綿、藻類など多様な生き物が依存して暮らしています。この生物多様性は、漁業資源や医薬品の開発資源としても重要です。また、サンゴ礁は天然の防波堤として高潮や波のエネルギーを吸収し、沿岸の浸食や被害を軽減します。さらに、観光資源としても大きな価値をもちます。
近年の研究によれば、サンゴ礁にはエビや魚、その他の生き物が発する多様な音が満ちており(参考1,4)、その音は数十km先にも届きます。
サンゴ礁に生息する魚はサンゴ礁やその周辺で産卵し、卵から孵った幼生は海流に乗って外洋で数日から数週間成長します。その後、幼魚はサンゴ礁に戻って棲みつきますが、その際にサンゴ礁の音を手がかりに集まってくることが、録音した音を再生する実験で確認されました。さらに海中を漂うサンゴの幼生もまた、音を頼りにサンゴ礁に引き寄せられることがわかってきました。このように、サンゴ礁の音環境は、生態系の維持や再生に欠かせない要素となっています。
しかし今、サンゴ礁は深刻な危機に直面しています。最大の要因の一つは、地球温暖化による海水温の上昇です。高水温が続くと、サンゴは共生藻を失い、白化現象を起こします。白化が長引けば、サンゴは栄養を得られず死滅します。さらに、沿岸開発やモーターボートの航行などによる騒音の増加も、サンゴ礁の「音の風景」に悪影響を与えています。健全な音環境が損なわれれば、幼魚やサンゴの幼生が適切な場所に定着できず、生態系の再生が妨げられる恐れがあります。
一方で、サンゴ礁の再生に「音」を活用する研究も進んでいます。健全なサンゴ礁で録音した音をスピーカーから流すことで、損傷したサンゴ礁に幼魚やサンゴの幼生を呼び寄せ、生態系の回復を促す試みです。こうした音による再生支援は、移植や保護区の設置といった従来の保全策と組み合わせることで、より効果的な修復につながると期待されています。
カメの音声コミュニケーション
無口な印象のカメも、さまざまな声を発していることが明らかになってきました(参考1)。その多くは、人の耳にはかすかにしか聞こえません。
アマゾンに生息するオオヨコクビガメは、毎年、何百kmも離れた場所から特定の砂浜に集まって産卵します。産卵後は、それぞればらばらに川へ戻っていきます。広大なアマゾンで、どのように同じ時期に同じ場所へ集まるのかは、いまだ謎です。
興味深いのは卵の中の現象です。卵は川沿いの砂浜に掘られた穴の中に産み落とされますが、その内部で、孵化前の胚(赤ちゃんガメ)が音を発していることが確認されています。仮説としては、同時に孵化するために、準備が整ったことを胚同士が伝え合っているのではないかと考えられます。同時に孵化すれば、きょうだいで協力して砂を掘り上げてそろって地表に出ることができ、捕食者に狙われるリスクを分散できます。
さらに母ガメも、子ガメの孵化に合わせて声を発し、子ガメたちが水へ向かう際には、水中から呼びかけるように声を出し続けます。その後、母子は一緒に川を下って森へと向かって行きます。発信機を用いた調査では、母子が80km以上の道のりを2週間かけて移動することが確認されました。カメは社会性の低い動物と考えられていたので、きわめて意外な行動といえるでしょう。
生物音響学が拓く新しい自然観
生物音響学の進展により、魚やサンゴ、カメといった、かつて音とは無縁と思われていた生物が、実は巧みに音を利用していることが明らかになってきました。こうした事実を知ったうえで彼らを見ると、これまでとは異なる思いや考えが湧いてきます。
これまで私たちが意識を向けなかった生物たちの音に耳を傾けることは、しばしば認識を揺さぶり、生態系への理解を深めます。それは保全のための重要な視点となるだけでなく、効果的な技術開発にも結びつく可能性を秘めています。
参考
1. カレン・バッカー著、和田佐規子訳、饒舌な動植物たち、築地書館、2024年
2. 生物音響学会HP
3. 赤松友成、木村里子、市川光太郎、水中生物音響学 声で探る行動と生態、コロナ社、2019年
4. アモリナ・キングドン著、小坂恵理訳、魚の耳で海を聴く 海洋生物音響学の世界、築地書館、2025年
5. アリストテレス、動物誌、第4巻、第8, 9章(紀元前4世紀)、アリストテレス全集7、岩波書店(1968年)より